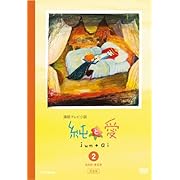ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論について紹介する後編です。今回は、「父-の-名」について、やはり内田樹著『寝ながら学べる構造主義』(2002 文春新書)をテキストに読解していきます。
「父-の-名」とは、言語活動を通じて、自分が「全能」ではないという事実を受け入れることです。
これは、フロイトのエディプスコンプレックス理論のラカンによる読み替えと考えられています。「エディプスコンプレックス」とは、ギリシャ悲劇の「オイディプス」において、オイディプスが父を殺し、母と交わるという内容から、幼児期(男根期)の子どもが母を手に入れて、父に抵抗するという、相反する心理的抑圧を指すものです。
『「エディプス」とは、図式的に言えば、子どもが言語を使用するようになること、母親との癒着を父親によって断ち切られること、この二つを意味しています。
-中略-
何か鋭利な刃物のようなものを用いて、ぐちゃぐちゃ癒着したものに鮮やかな切れ目をを入れてゆくこと、それが「父」の仕事です。ですから、「父」は子どもと母との癒着に「否」(Non)を告げ、(近親相姦を禁じ)、同時に子どもに対して、ものには「名」(Nom)があることを(あるいは「人間の世界には、名を持つものだけが存在し、名を持たぬものは存在しない」ということを)教え、言語記号と象徴の扱い方を教えるのです。』
切れ目を入れることと名前をつけることは、同じ一つの身ぶりだと内田は言っています。
『アナログな世界にデジタルな切れ目を入れること、それは言語学的に言えば「記号による世界の分節」であり、人類学的に言えば「近親相姦の禁止」です。
-中略-
ことばを学びつつある子どもは、いま学びつつある母国語がどのようなルールに基づいて世界を分節しているかは分かりません。
-中略-
「羊」について「ムートン」という語だけを持つ言語共同体の中で育ったものと、「シープ/マトン」の二つの語を持つ言語共同体の中で育ったものでは、「羊」の見え方がはじめから違います。ことばを学ぶ子どもはそれを「まるごと」受け容れる他ありません。
子どもが育つプロセスは、ですから言語を習得するというだけでなく、「私の知らないところですでに世界は分節されているが、私はそれを受け容れる他ない」という絶対的に受動的な位置に自分は「はじめから」置かれているという事実の承認をも意味しているのです。
-中略-
この世界は「すでに」分節されており、自分は言語を用いる限り、それに従う他ない、という「世界に遅れて到着した」ことの自覚を刻み込まれることをも意味しています。』
内田は、物語の多くがこの「エディプス」的機能を果たしているとして、童話『こぶとり爺さん』を取り上げてその事実を確認していきます。頬に大きなこぶのあるお爺さんが鬼の前で踊ったところ、鬼に気に入られてこぶを取ってもらいます。この話を聞いたやはり頬に大きなこぶのある別のお爺さんが同じように鬼の前で踊ったところ、今度は不評で新たにこぶをつけられてしまうという童話です。
「芸は身を助ける」、「努力は報われる」、「よいお爺さん、悪いお爺さん」といった合理的説明による説話は、リライトした作家による改作であり、そのような「つまらなさ」を何世紀も語り伝えるはずもない、と断った上で次のように続きます。
『この物語の教訓は「この不条理な事実そのものをまるごと承認せよ」という命令のうちにこそあるのです。
この物語の要点は「差別化=差異化=分節がいかなる基準に基づいてなされたのかは、理解を絶しているが、それをまるごと受け容れる他ない」と子どもたちに教えることにあります。
-中略-
「鬼」とは、ある差異化が行われた後になって、「<誰か>が差異化を実行したのだが、その差異化がどういう根拠で行われたのかは決して明かされない」という事実を図像的に表象したものです。つまり「鬼」というのは存在する「もの」ではなく、「世界の分節は、<私>が到来する前にすでに終わっており、<私>はどういう理由で、どういう基準で、分節がなされたのかを遡及的に知ることができない」という人間の根源的な無能の「記号」なのです。
頬のこぶの「切断」というエピソードは、世界の言語的「分節」が、そのまま「去勢」(それは「父の否」が特に子どもに対して権力的に発動したときの暴力的な相を示すことばです)と同義であることを正しく示しています。
-中略-
そのようにして私の外部に神話的に作り出された「私の十全な自己認識と自己実現を抑止する強大なもの」のことを精神分析は「父」と呼びます。』
* 以上『 』内記述は、内田樹著『寝ながら学べる構造主義(文春新書 2002)』より抜粋
前回の「鏡像段階」と今回の「父-の-名」は、子どもが成長する過程で直面し、乗り越えるべきふたつの段階です。そしてこの人間の全能性の否定というテーマは、様々な、実に多くの神話に、民話に、宗教に、社会理論に・・・あらゆる場面で同形の説話構造をもって受け継がれていきます。
そしてNHK連続テレビ小説『純と愛』もまた、このことから読解することが可能になります。
主人公の純は、おじいから「純はそのままでいい」と言われたことにずっと囚われています。これは「私」の全肯定であり、つまり純は、全能感の内にいる点で「子ども」を表象しています。だから「私」の論理でしか「私の外部」に触れることができない。全能の「私」ゆえに「まほうのくに=ユートピア(現実に存在することのない理想郷)」の実現へハンドルするのです。当然、純の発することばは、行動は、周囲と不協和音を生じます。
「エディプス」として機能すべき「母」、「父」はどうでしょう。母晴海と純との癒着は純の兄弟のなかで極めて弱い。癒着をおじいが担うとともに晴海は、夫善行の囚人でもあるのです。善行は、純に対して「父」であろうとしますが、「母」が機能せずに純の癒着が別のレイヤー(おじい)にある点で、こちらも機能しない。善行がまくしたてる四字熟語(ことば)が表層を滑っていく、これが「父」の機能不全を表しています。おじいは晴海の父であり、亡き人であることがこのことを強化してもいます。
純の恋人、後の夫である愛(いとし)は、純の対極をなす人物として描かれます。つまり呪いとも言うべき無能感に蝕まれた人間としてです。愛は、双子の弟を亡くしていますが、このことはつまり、鏡像段階の鏡に映った自己(像)の消滅を意味します。
何もできないが全能感によって私的世界を構築している純と、何でもできるが無能感によって世界と関わることができない愛が互いを求めるのは、相互の欠落(鏡像段階、エディプスのそれぞれの欠落、あるいは失敗)を相補することで外の世界とかろうじてつながるという点で必然なのです。
愛は純に「純さんは、ずっとそのままでいてください」と繰り返します。このことばは、物語中盤まではおじいのことばの代替として、純を駆動させるエンジンとして機能していました。しかし中盤以降では、「エディプスの失敗ゆえの<純粋>を保持し続けて世界とつながりなさい」に意味の移行がなされているように思います。最終回の純の決意表明ともいうべき「透明な」ことばは、純自身の欠落、愛のことばの意味を「まるごと承認して大人になる」、つまりエディプスの達成、というか克服を意味するのです。
これは、純の「自立=大人になること」であり、それゆえ愛は、物語において役目を終えて退場せざるを得なかったのではないか、僕はそのように思います。
最後に、物語を俯瞰しての作品のメタメッセージとは何かを記すことにします。
純が目指した「まほうのくに」は、ユートピアの不可能性において当然ながら実現しません。就職したホテルは外資によって実質買収され、おじいのホテルはつぶれ、再就職したホテルは焼失し、最後の自身が立ち上げたホテルは台風の被害でオープンできないままです。この全ては、外的要因によってもたらされた「不条理」なものです。
つまり内田樹の『この物語の教訓は「この不条理な事実そのものをまるごと承認せよ」という命令のうちにこそあるのです。』が全てであり、物語内部で失効した「父」が、メタレベルで再帰的に登場するものだといえます。
ですから物語を通じて純と愛のかたわらに「ねむりひめ」があることが示すように、『純と愛』は、童話であるといえるのでしょう。