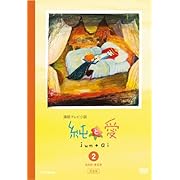ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論からNHK連続テレビ小説『純と愛』を読解する、というのが前回書いたことでした。僕は、ここから少なくとも二つの事柄を抽出して論じることができると思います。
「僕は、ここから少なくとも二つの事柄を抽出して論じることができると思います。」
この一文は、なんだかおかしな印象を受けます。なぜなら、「ここ」が指す「ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論からNHK連続テレビ小説『純と愛』を読解」した文章は、僕が書いたものなんですから。
「僕は、ここからさらに二つの事柄を論じることを試みます。」でもいい気がします。でも僕は、そのように書かなかった。
「作品=テクスト」は、作家が意図した設計図の全てが滞りなく実現したものではありません。そもそも作家の頭の中には、完成を見越して完全にコントロールできる設計図など存在していません。書きながら、つくりながら枝葉が広がるように、時にはあらぬ方向へとさまよい、それを修正し、けれど制御の効かないままに、なのにそのようにしかならないものとして現出するもの。つまり作品は、作家の手から離れて「自立」しています。
この「作品=テクスト」の「自立」において、作品に対峙すること、批評することの多様性の獲得が、ロラン・バルトの「テクスト」理論です。
僕は、前回書いたものから、その時点で、新たに二つの事柄について展開していくことを意図していたわけではありません。書いたもの=テクストについて「気づき」があって、はじめて二つの事柄を書こうと思ったのです。このことは、作家自身も「作品=テクスト」の外側にいて、評者、読者、観客として振る舞うことを許してくれる、否、というよりもそのようにしか振る舞えないことを表しています。
僕は、建築設計者として、ブログ書きとして、大学や専門学校で学生の作品を批評するものとして「テクスト」理論を駆使してします。僕を駆動させているエンジンといってもいいくらい重要なものです。
「テクスト」理論については、次回以降でやはり内田樹著『寝ながら学べる構造主義』(2002 文春新書)を教科書として詳細に読解していきます。
それでは、前回ブログから僕が「気づいた」二つの事柄について、記すことにします。
ひとつは、『純と愛』における「社会が包摂性を失っていくこと」によって、僕らが生きるこの世界はどうなっているのか、ということです。『純と愛』の脚本家遊川和彦は、『家政婦のミタ』(2011)で家族幻想が解体して後の家族という共同体を扱っていますが、『純と愛』では、共同体幻想の解体をより多層化して表現しています。共同体とは、個人を包摂する社会的な規範であって、家族、学校、会社、地域コミュニティ等、様々なレイヤーで機能しています。共同体幻想が解体していく過程については、以前に東浩紀、宮台真司、小熊英二を通じて触れていますので、そちらをご覧いただけると幸いです。
共同体幻想が解体していけば、個人を縛る規範が解体されるわけですから、僕らは当然自由になります。同時に、もの・ひと・情報の流動性が拡大して、こうした状況に裸でさらされることにもなります。この、もの・ひと・情報の流動性が拡大した社会は、高度資本主義経済と極めて親和性が高い。こうした社会状況に対応して上手にサーフィンできる人にとっては、こんなに素敵な社会はないと思います。しかし一方で、この流動性の波に乗れない人だっているわけで、そうした人は、足場(共同体)を確保できないままに立ちすくむことになります。
どこにも自分を包摂してくれる場所がないというのは、孤独であり空虚でもあります。そしてついには、こうした事実に耐えられなくなります。
で、どうなるのか。
大澤真幸によれば「アイロニカルな没入」、宇野常寛であれば「あえて、ベタに、決断主義的にコミットする」ことになります。
つまり、対象の真意は、正誤は分からないけれど、自己選択、自己決定によって何かに没入、コミットすることで、自己承認欲求を満たそうとするのです。自己承認欲求は、コミットする対象が強固なものであるほど最大値化して満たすことができるはずです。ですから選択において、中庸はありえません。また、たとえ「僕は自己決定によって何かにコミットしない」と考えたとしても、「何かにコミットしない」ことを決断主義的に決定している点で、「アイロニカルな没入」の外へ出ることもできないのです。
ラウドマイノリティでもサイレントマジョリティでもその不気味さは、時に消費者の、あるいは弱者のペルソナを用いて駆動する(なぜなら審級は、消費者、ユーザー、プレイヤーの側にあるのですから)点で、自己承認欲求を満たすための「アイロニカルな没入」のひとつの表出と見ることができます。
僕らは、『純と愛』で「全能感ゆえの自己承認欲求の最大値化された主人公」を自分の鏡像として見ています。同時に「社会的包摂性が解体された後の世界」も体験しています。だからイライラしてしまう。目を背けたくなるような事実を突きつけられるわけですから。
暗い、実に暗いなあと思いながらも人ごとではなくて、この文章を自戒の念を込めて書いています。
メタメッセージが「私を承認しなさい」で溢れていくことと、それは社会的包摂性の解体によって引き起こされていること。僕が現時点でできることは、こうしたことを乗り越える想像力をブログで紹介すること、建築設計において新たな共同体のあり方を模索しながら包摂性を実現できるような住宅をつくること、それから僕自身が「私を承認しなさい」というメタメッセージ(これは最も創造性のない不愉快なこと)を発信しないことです。
しかしNHK朝の連続小説は、えらいですね。『純と愛』に対する苛立ちを続く『あまちゃん』がちゃんとすくいとってくれるのですから。そう、この物語は、社会的包摂性のおはなしです、たぶん。
そして、この脚本家遊川和彦から宮藤官九郎へのバトンの受け渡し(当然両作品とも東日本大震災について一方は暗喩として、他方は直接的に描いていると思われますが)を考えると、東日本大震災の起きた2011年に放映されたドラマ、『家政婦のミタ』(脚本遊川和彦)、『11人もいる』(脚本宮藤官九郎)、『マルモのおきて』についても今後触れておく必要があると思います。すべて家族幻想が解体された=社会的包摂性を失った後の家族についての物語です。
気づきの二つ目は、建築家イームズ夫妻の「Powers of Ten」(1968)からものの見方について考える、ということでしたが次回後編で記すことにします。