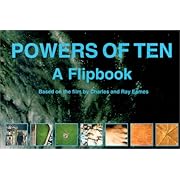「ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論からNHK連続テレビ小説『純と愛』を読解する」というのは、一見して全く異なる事象を結んでいます。ともすれば論の組み立てそのものが疑わしい。そうしたあやうさの上で、しかしそうでしかないものとして読解するということを「視点の移動」について、建築家イームズ夫妻の映像作品『Powers of Ten』(1968)を参照して論じます。
男性の姿を上部から撮影するこの映像は、視点(カメラ)の上昇とともに撮影する範囲を拡大していきます。男性から公園へ、公園から街並へ、ついには宇宙空間にまでその範囲は広がっていきます。次に視点(カメラ)は降下を始め、1分で元の男性にまで行き着くと、こんどは男性の手の甲へ、そこからミクロの世界へ突入していきます。
これは、1m×1mの世界から10秒で10m×10mへ、さらに10秒かけて100m×100mというズームアウトと1m×1mの世界から10秒で0.1m×0.1m、次の10秒で0.01m×0.01mというズームイン、つまり「視点の移動」を表現しています。
この作品がつくられた1968年当時、CGのない時代において、実写からアニメーションへのシームレスな映像の移行、また、素粒子への見地が一般化していない状況でのミクロの世界の表現は驚嘆すべきことでした。しかし、ここで論じる重要な点は、「視点の移動」そのものにあります。
近代的なツリーモデルを参照するならば、ジャック・ラカンの哲学的見地による思考はツリーの上層に位置していて、他方『純と愛』は大衆的な娯楽、サブカルチャーという点で下層に存在するものです。この階層の異なる二つの事象を結ぶには、常に視点を移動しながら観察して、両者の連関、あるいは相似について「発見」する必要があります。引きと寄りと言ってもいいですし、抽象度を上げる、下げると言ってもいい。あるいはオブジェクトレベルとメタレベルで論じると言ってもいいのですが、「視点の移動」こそが、「世界を構成する根拠」にたどり着いてこれを表象する武器のひとつになり得ると僕は考えています。
ここでひとつの疑問が生じます。僕たちは、ポストモダンの進行する状況を生きています。ツリーモデルは失効して、かつて上部構造を形成していた事象はドロップしてしまう。あらゆるものは要素に解体されて、フラットにデータベース化されています。そのような世界においては、ジャック・ラカンの哲学的見地も『純と愛』も相対化されて並列しているではないか。ならば、階層を越境する縦軸の「視点の移動」ではなく、島宇宙を横断して対象を結んでいく横軸の「視点の移動」こそが重要なのではないか、と。
レオナルド・ダ・ヴィンチは、「木の枝と血管のアナロギア」という素描を残しています。これは、樹木の枝と血管が重ね合わせられたスケッチですが、自然界における「かたち」の「類似」についての考察です。現在の科学的認知では、自然界でつくられる「かたち」のパターンに共通する構造構築原理を見ることができますが(『福岡ハカセの本棚』2012 メディアファクトリー新書参照)、ミシェル・フーコーによれば、ルネサンス期には「類似」が知を構築する役割を演じてきました。例えばトリカブトの「かたち」の記号的類似として人間の眼が挙げられ、眼病に効くとされたようにです。
この時代、科学と芸術は渾然としたものでしたが、「かたち」の「類似」を用いてどこまでも世界を構築する知を横滑りさせることが可能でした。しかし僕らが生きるこの世界では、要素がデータベース化されて並べられているだけで、それらは独立した欠片として存在しているに過ぎません。そして僕らは、単に(かたちの)「類似」をもって対象間を結んでいるわけでもありません。僕らは、データベースを消費する審級として、引きと寄りを繰り返し、ときに対象に没入し、他方で俯瞰しながら要素をピックアップしてコラージュしているのです。
僕が「視点の移動」と言っているのは、ツリーモデルにおける「縦軸の視点の移動」でも、ポストモダン世界のリゾームモデルにおける「横軸の視点の移動」でもありません。先に記したように、引きと寄り、抽象度を上げる下げる、オブジェクトレベルとメタレベルで論じるということです。被写界深度をかえる、という言い方でもいいかもしれません。
ですから、対象間を単純に横断していくだけでは「世界を構成する根拠」にたどり着くことは難しい。僕たちは、対象間を横断しながら、同時に常に「視点を移動=被写界深度をかえ」てものを見ることに慣れる必要があるのではないか。もはや審級が消費者、ユーザー、プレイヤーの側にある点で、こうした視点の獲得こそ僕らに与えられた特権でもあるのですから。
ロラン・バルトの「テクスト」理論によれば、「作者」が後退して「対象(作品)=テクスト」のみがある。このときテクストのほうが僕たちを「テクストをいかようにも読み込む主体」として形成して行く点で、(テクストと僕らの絡み合いにおいて)「読者」が誕生し、批評が成立するのです。しかし、先に述べた「視点の移動」を持ち得ない限り、僕らの読解は、対象とするテクストの囚人としてしか振る舞えない、ともいえます。ゆえに次回、ロラン・バルト「テクスト」理論 -構造主義- を論じるにあたり、先んじて「視点の移動」を用いて「テクスト=作品」に対峙することを記すにいたったわけです。