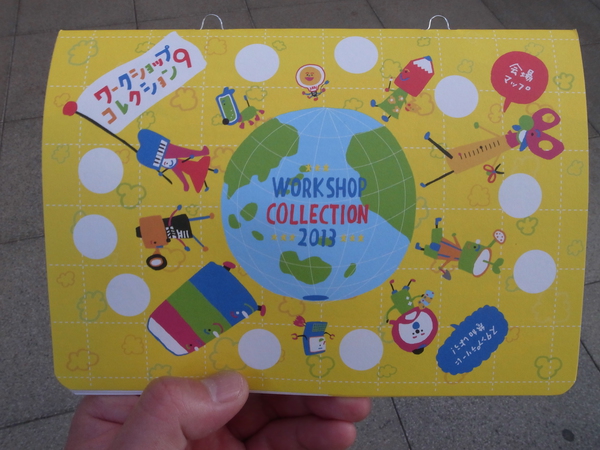ブログの更新が滞っていました。
「インフラが整備された」社会状況とは何かについて論じている途中でした。「インフラが整備されていくというのはどういうことか、誰がどのように整備しているのか、そしてインフラが整備されて世界とはどのようなものなのか」という問いを立て、「構造主義」のいくらかの知に当たること。そこから「権力の行使」について目的的に論じることを試みようとしていました。
この話は、まだ途中ですので、今後さらに展開していこうと考えていますが、僕の身の上で転機が訪れましたので、そのことを先行して書いていこうと思います。
ロラン・バルト「テクスト」理論は、読解の多様性を肯定するものでした。これに続いて書いたジャック・デリダ「幽霊」とは、読解の多様性が持つ、ああも言える、こうにもなれる、という変更可能性(幽霊)ゆえに、再帰的に作品=テクストがそうでしかないものとして立ち上がる、ということだったと思います。
では、僕らが生きるこの世界において、これら「知」が教えてくれることは、一体どのようなものなのでしょうか。僕が大学生、専門学校生と関わることで体験した事象について、「テクスト」、「幽霊」から考えてみたいと思います。

「ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論からNHK連続テレビ小説『純と愛』を読解する」というのは、一見して全く異なる事象を結んでいます。ともすれば論の組み立てそのものが疑わしい。そうしたあやうさの上で、しかしそうでしかないものとして読解するということを「視点の移動」について、建築家イームズ夫妻の映像作品『Powers of Ten』(1968)を参照して論じます。

ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論からNHK連続テレビ小説『純と愛』を読解する、というのが前回書いたことでした。僕は、ここから少なくとも二つの事柄を抽出して論じることができると思います。
「僕は、ここから少なくとも二つの事柄を抽出して論じることができると思います。」
この一文は、なんだかおかしな印象を受けます。なぜなら、「ここ」が指す「ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論からNHK連続テレビ小説『純と愛』を読解」した文章は、僕が書いたものなんですから。


僕は、以前次のような問いを立てました。
「社会が変異して働き方が変わり、住環境が変わり、地域コミュニティが解体され、人とのつきあい方が変わり、家族幻想が崩壊しているのに、どうして地域の特性が失われ、郊外は、住区は、商店街は、住宅は均質になっていくのか」

村上春樹は、文章を書くことを、自分の内側に潜っていくことだと、『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』(2010 文芸春秋)に書いています。これについて、内田樹が『街場の文体論』(2012 ミシマ社)で触れています。


村上春樹は、この「自分の内側に潜っていく」ことを「鉱脈」という言い方で表現したり、「暗闇」、「井戸」、「地下室」という比喩を使ったりするそうです。
近代のツリーモデルが機能不全を起こして失効し、セミラチス、あるいはリゾームへと変異していく過程、またそのモデルについて書いてきました。

東浩紀は、このポストモダンの進行する状況での消費の特性を「データベース消費」と呼びます。これは、1980年代の日本で示されることの多かった『深層が消滅し、表層の記号だけが多様に結合していく「リゾーム」というモデル』よりも、ポストモダンの世界を記述するのに「データベース・モデル」で捉えた方が理解しやすいこと、によります。
慶応大学日吉キャンパスで開催されたワークショップコレクションレポートの後編です。
ここでは、武蔵野美術大学建築学科3年生の有志による竹シェルターをご紹介します。

2013年3月9日と10日、NPO法人CANVAS、KEIO MEDIA DESIGN主催によるワークショップコレクションが、慶応大学日吉キャンパスで開催されました。
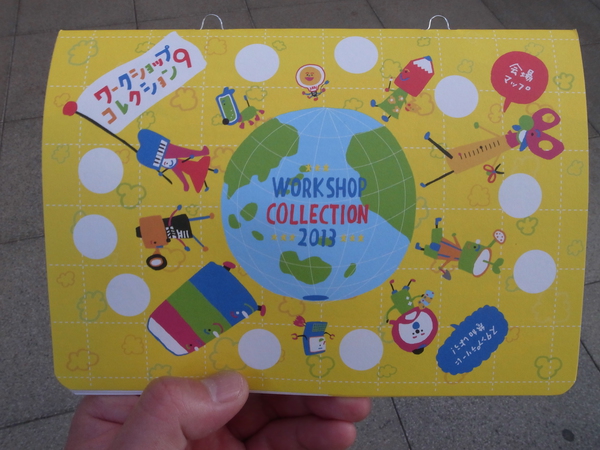
ワークショップコレクションは、こども向けワークショップ・プログラムの全国普及と発展を目的に、全国に点在するこども向けワークショップを一同に集め、一般へ広く紹介する博覧会イベントです。
ここには様々な団体が参加しており、この2日間で開催されるワークショップは、実に100に上ります。
以前武蔵野美術大学建築学科のスケッチ会をレポートしました。同会の主催者のひとりである小林敦さんが、今回のイベントに参加している「chick こどもの創造のくに」のワークショップに関わられています。ご連絡いただいたので行ってきました。
近代と呼ばれる時代が解体されていく経緯について、東浩紀、宮台真司、小熊英二を参照しました。
ここではその後の時代、つまり今現在僕たちが生きるこの世界の「モデル」について、やはり東浩紀著『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会(講談社現代新書 2001)』を参照しながら考えたいと思います。

その前に、クリストファー・アレグザンダーの論文、『都市はツリーではない(1965年)』について触れておきます。