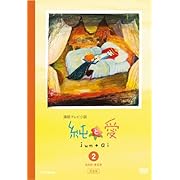ロラン・バルト「テクスト」理論とは、読者は作品を作者から切り離してこれに対峙し、さまざまな要素によって織り上げられたテクストを能動的かつ創造的に、多様に読むことを許す、というものでした。
これは、極めてポストモダン的な思考といえます。西欧形而上学における表層から深層への一方向性と、その最深部には真理があるという考え方への批判的批評によるものだからです。作品をつくるということは無からの創造であり、創造主である作者にこそ審級がある、読解とは、作品を通じて作者=審級=真理に触れる作業であり、その意味において読者は受動的な観客である、ということに対する批判。
つまりツリーモデルの解体を行っているのですが、この点で「テクスト」理論は、以前本ブログで紹介しました東浩紀「データベース消費」と同義であるといえます。

ロラン・バルト「テクスト」理論についての中編です。
前回は、言語運用における三つの「不可視の規制」である「ラング」(langue)、「スティル」(style)、「エクリチュール」(écriture)について書きました。
ラングは、言語運用を外側から規制する母語、スティルは、内側から規制する個人的で生得的な言語感覚を表し、これらに個人的選択の余地はありません。一方でエクリチュールは、選択においての自由があり、しかし選択した時点で「自分の選んだ語法が強いる型にはめこまれてしまう語り口、ことばづかい」というものでした。
内田樹は、テクスト自体が内在する「エクリチュールによる言語運用の不可視の規制」によって、「テクストのほうが私たちをそのテクストを読むことができる主体へと形成してゆく」と言っています。
『テクストと読者のあいだにこのような「絡み合い」の構造があることに気づき、それを批評の基本原理に鍛え上げたこと、それがバルトのテクスト理論家としての最大の業績です。
-中略-
このテクストと読者のそれぞれがお互いを基礎づけ合い、お互いを深め合う、双方向的なダイナミズムに基づいて、バルトはテクストについてのまったく新しい理論を紡ぎ出すことになります。』
それでは、ロラン・バルト「テクスト」理論 -作者の死-について。

僕らは、作品を鑑賞し、あるいは批評するとき、しばしば作品の根拠を「作者」に求めようとします。「作者」の思考において、「作者」の性格において、「作者」の原体験において、というように。
例えばゴッホの絵画を彼の狂気に、ピカソについて彼の性愛に、シャガールであれば彼の無垢な愛に作品の根拠を見いだす、つまり作者の意図を正確に読み込むという受動的な作業を通じて、作品を理解しようとしているのです。
ロラン・バルト(1915〜1980)は、『物語の構造分析』に収録されている「作者の死」の中で、そのような作者の打ち明け話を批判した上で、作品の根拠を作品それ自体に求めることで「読者が主体的に作品を創造する」ことの重要性を説いています。こうした考えを「テクスト理論」といいます。
内田樹著『寝ながら学べる構造主義』(文春新書 2002)を教科書に、「テクスト」理論について理解したいと思います。

ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論からNHK連続テレビ小説『純と愛』を読解する、というのが前回書いたことでした。僕は、ここから少なくとも二つの事柄を抽出して論じることができると思います。
「僕は、ここから少なくとも二つの事柄を抽出して論じることができると思います。」
この一文は、なんだかおかしな印象を受けます。なぜなら、「ここ」が指す「ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論からNHK連続テレビ小説『純と愛』を読解」した文章は、僕が書いたものなんですから。

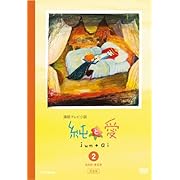
ジャック・ラカン(1901〜1981)の「鏡像段階理論」と「父-の-名」の理論について紹介する後編です。今回は、「父-の-名」について、やはり内田樹著『寝ながら学べる構造主義』(2002 文春新書)をテキストに読解していきます。

ポストモダン状況が進行するこの世界における「インフラが整備されていく」ことを理解するために、構造主義をガイドとして論じる第一回です。これを解く鍵として、ミシェル・フーコーが提示する「権力の行使」について当たるのが最良だと思います。ですが、あえて迂回し、構造主義的知のいくつかに触れながらそこへ到達することを試みたいと考えています。たとえ直接的到達が不可能であったとしても、この世界を生きる想像力を提示することは、意義あることだと思うので。
今回は、ジャック・ラカン(1901〜1981)について。

僕は、以前次のような問いを立てました。
「社会が変異して働き方が変わり、住環境が変わり、地域コミュニティが解体され、人とのつきあい方が変わり、家族幻想が崩壊しているのに、どうして地域の特性が失われ、郊外は、住区は、商店街は、住宅は均質になっていくのか」

近代のツリーモデルが機能不全を起こして失効し、セミラチス、あるいはリゾームへと変異していく過程、またそのモデルについて書いてきました。

東浩紀は、このポストモダンの進行する状況での消費の特性を「データベース消費」と呼びます。これは、1980年代の日本で示されることの多かった『深層が消滅し、表層の記号だけが多様に結合していく「リゾーム」というモデル』よりも、ポストモダンの世界を記述するのに「データベース・モデル」で捉えた方が理解しやすいこと、によります。
近代と呼ばれる時代が解体されていく経緯について、東浩紀、宮台真司、小熊英二を参照しました。
ここではその後の時代、つまり今現在僕たちが生きるこの世界の「モデル」について、やはり東浩紀著『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会(講談社現代新書 2001)』を参照しながら考えたいと思います。

その前に、クリストファー・アレグザンダーの論文、『都市はツリーではない(1965年)』について触れておきます。
近代からポストモダンへの以降状況について、以前東浩紀、宮台真司をとりあげましたが、より具体的に理解するために小熊英二をご紹介します。
小熊英二著『社会を変えるには(講談社現代新書 2012)』